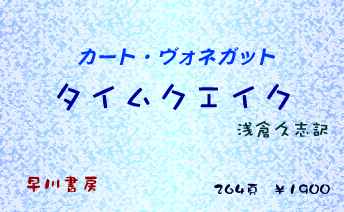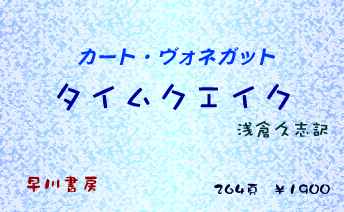ヴォネガット風シチューと自由意志
竹内真
(作家)
以前、ある学生とこんな会話を交わしたこ
とがある。僕の小説を読んでくれた彼から、 いやに真面目な顔つきで質問されたのだ。
「この作品の中で、作者の訴えたかったことは何だったんですか?」
「……別に訴えたいことなんかないよ。国語の試験問題じゃないんだから」
「それはおかしいですよ。小説を書くには芯になる主張みたいのが必要でしょう?」
「え、そうだったの?」
「…………」
彼は呆れてしまったらしく、それ以上は何
も尋ねてこなかった。──作者の主張を百字 以内で述べてくれなどと言われないだけ幸運
だったが、受験用の国語教育というのはそこ に必ず答えがあるはずだという強固な固定観
念を生み出すようだから油断がならない。
小説というのは本来とても自由な表現形態だと思うのだが、どうも世間ではそう思われ
ていない節がある。小説はかくあるべしという信念のようなものが確固として存在してい
て、「こんなものは小説ではない」だの「小説には○○が無ければならない」だのといった言
説はあちこちで耳にする。作家が自らの方法論に基づいて言っているだけならともかく、
読者の側にも似たような意見は多いようだ。
村上春樹の『ねじまき鳥クロニクル』が、
文壇のみならず一般読者の間でも物議を醸し たのは記憶に新しい。否定的な意見において
は謎が未解決だとかテーマが不明確だとかい う問題が指摘され、中には批評の域を飛び出
して本気で怒っている人もいた。──裏を返 せば、それだけ「謎は解決するべし」「テーマは明確に」といった小説観が力強くはびこっているということかもしれない。
「小説」という言葉を「文学」に置き換えてみると事態はいっそう混迷を深める。僕は
文学に関しては小説以上に無知なので言及は控えるが、とにかく固定観念が自由な発想を
阻みかねないのは理の当然で、それが表現活動における障壁になるのは想像に難くない。──かくいう僕自身、ともすると形式に縛られ、書きかけの小説で行き詰まったりしているのだから世話はないのだ。
さて、ヴォネガットである。
カート・ヴォネガットの最新にして最後の作品、『タイムクエイク』は、小説に対する様々な固定観念
を軽々と蹴飛ばすような迫力を持っている。 この作品が発表された1997年の時点でヴ
ォネガットは74歳の高齢だったらしいが、 衰えなどは微塵も感じさせない力作は小説に
関する様々な刺激に満ちていた。
まず、その形式がまともではない。『タイムクエイク』は小説と見なされてはいるもの
の、作品中ではヴォネガットの随想が占める割合もかなり大きいのだ。元々フラグメンタ
ルな作風の彼の作品群の中でも、小説とエッセイと自叙伝の融合とも言うべき『タイムク
エイク』のあり方は際立って特異である。
ヴォネガットはまず、まっとうなフィクション作品としての『タイムクエイク』(ヴォ
ネガットはこれを『タイムクエイク1』と呼んでいる)を完成させた。しかし本人の評価
によれば「できそこない」であり、彼はそれを発表することを良しとしなかった。『タイ
ムクエイク1』を「おろして切り身に」し、「あらは捨てて」しまうことにしたのだ。そ
の切り身に彼の随想を加え、まとめて煮込ん でシチューに仕上げたのが、最終的に刊行さ
れた『タイムクエイク』なのである。
従ってこの『タイムクエイク』は、小説や
エッセーとしての側面だけでなく、『タイム クエイク1』に対する批評や小説論としての
顔も持っている。そうした様々な要素がシニ カルでコミカルな調味料でまとめられ、ヴォネガット特有のアフォリズムでしめくくられ
ているのだ。──小説・随筆・評論とくれば、まるで文芸雑誌のような品揃えである。
さらにこのシチューには、作中人物のキルゴア・トラウトが書いたとされる短編小説も
数多く含まれている。その意味でメタフィクションでもある上、メイキングオブ『タイム
クエイク』とでもいうべきプロローグ、読者欄のような趣さえある訳者あとがきと、一冊
の本が実に多彩な顔を持っているのである。
そうした重層構造がシチューの味に奥行きを与え、読者をして再読に駆り立てる。内容
だけでなく、構造そのものが読み手の思考を刺激してやまないのである。固定観念に縛ら
れた目で見れば破綻したわけの分からない作 品かもしれないが、小説というのは何でもあ
りのメディアなのだということを確認するためには最高の素材だと言えるだろう。──少なくとも、どっかの新人賞に投稿する前に読
んでおいても損はないんじゃないかと思う。
世界や歴史に対する愛情と皮肉に満ちた視点は米文学界の老大家でなければ持ちえない
ものかもしれないが、その大胆な手法や奇抜 な筋立てには学ぶものが多い。彼の作家とし
ての姿勢は固定観念への戒めにもなるはずだ。──最後に、その粗筋に軽く触れておこう。
膨張を続ける宇宙がある日突然くしゃみをし、ほんの少しだけ収縮する。そのため時空
連続体は十年ほど前に遡り、2001年の世界はいきなり1991年の世界に戻る。
全人類がその10年をやり直すことになる。
過去を変更することはできないから、10年間 をそっくりそのままリプレイするはめになる
のだ。──まるで小説という表現形態そのも ののメタファーのように。
延々と続く既視感の中、人々は自らの意志
を失い、リプレイが終わった時には呆然と立 ち尽くすことしかできない。必然的に大混乱が起こるが、それを鎮めようと活躍するのは
不遇の老作家キルゴア・トラウトである。
2001年のニューヨーク。この時震現象にもうろたえなかったトラウトは、人々の目
を覚まさせるために大きく声を上げるのだ。 ──自由意志! 自由意志!
*この書評は1998年にとある文芸雑誌に掲載される予定として書かれましたが、都合により掲載されなくなったものです。評者・竹内真さんのご許可をいただき、CPABRでの掲載の運びとなりました。